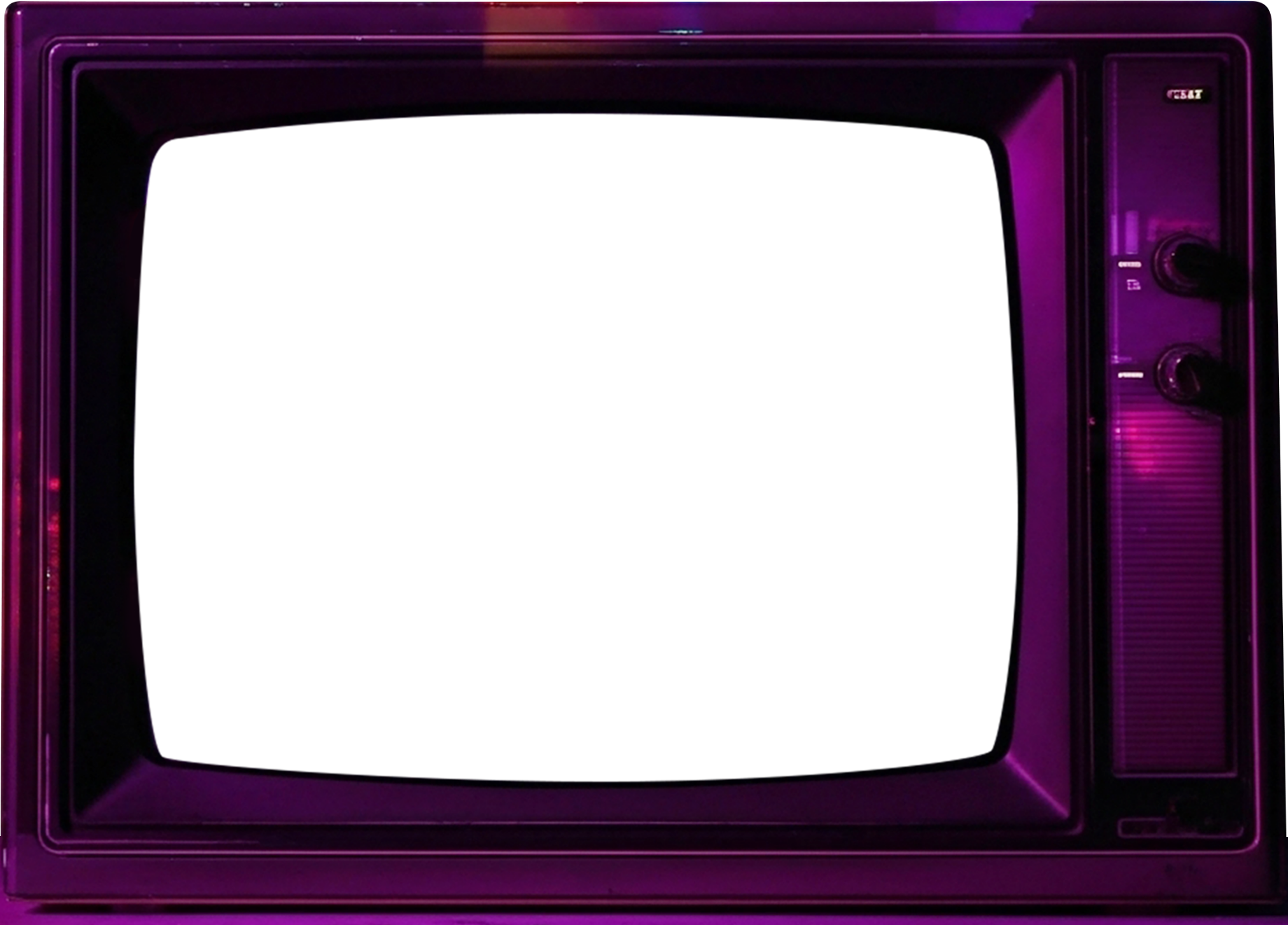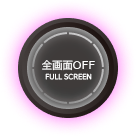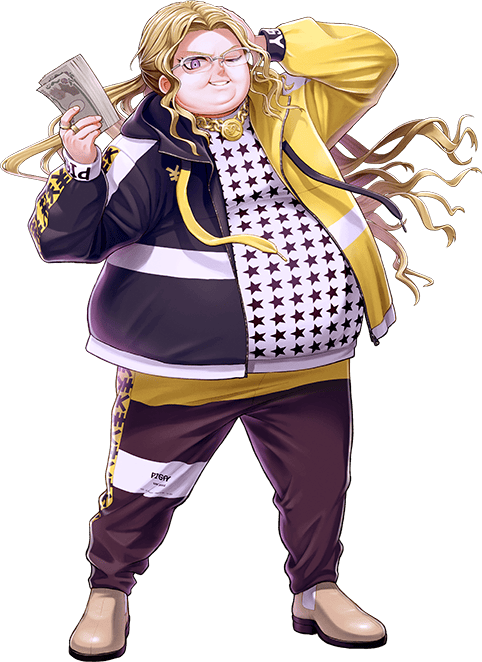11話「カズキの推理」
<青山カズキ>
「みんな、ガレキ山での人助けお疲れ様。お疲れのところ悪いけど、急いで話したいことがあるんだ」
隠れ家に戻って早々、カズキはメンバーを全員集めて会議を開始した。
<青山カズキ>
「いろいろ腑に落ちない事があってさ…まずはマウンティング力の事だ。
僕はこの判定はシステムがやってるものと思っていた」
<五反田豊>
「確かに…そう言っていましたね」
<青山カズキ>
「けど冷静に考えれば…優越感みたいな曖昧なものを機械が判定するなんて、やっぱり難しいはずなんだ」
言われてみれば確かにそうかもしれない、と曜は思う。
マウンティング力なんて曖昧な概念を数値に置き換えるなんて、どんな高度なAIにだって不可能だろう。
<千羽つる子>
「つまり…どういう事ですか?」
<青山カズキ>
「判定は人間がしているのかもしれない」
<黒中曜>
「そんな事できるのか?」
ミナトシティに住むたくさんの人間のマウンティング力を計測するなんて、それこそ人間業ではないと思うが――
<青山カズキ>
「理論上は可能だよ。テクノロジーを駆使すればね。まず、アプリそのものから音声などのデータが送られている可能性がある。
それと、街に不自然に設置された異常な数の監視カメラ…」
<小日向小石>
「さっき住宅街で見たやつだね…」
<青山カズキ>
「僕達が勝手に大層なものを想像していただけで、この街で起きている事は、実は茶番なのかもね」
呆れたように言ってスマホの画面を見るカズキ。
<彩葉ツキ>
「じゃあ…誰がそんな事してるの? ゼロに雇われてる人?」
<青山カズキ>
「腐っても統治ルールの根幹に関わるような仕事だ。お金で雇われたような相手に任せられるかな?
たとえば…ゼロに脅されて仕方なくやらされてる人とか。あるいは――」
<五反田豊>
「それをやるメリットがある人間…ですか?」
五反田が眼鏡を光らせる。
<青山カズキ>
「その線が強いかな。まあ、あくまで推測だけどね。いや、証拠もないから想像止まりか…」
<彩葉ツキ>
「もし、そんな人達が本当にいるなら、マウンティング力上げてってお願いできるのになー」
<青山カズキ>
「チマチマ上げるより手っ取り早いのは間違いないね。けど…残念ながら僕らには連絡手段がない。
それが誰なのか、アタリも付いていない状態だ」
<小日向小石>
「じゃあ、結局これまで通り上げていくしかないって事?」
<青山カズキ>
「今はやれる事をやるしかないかな…改めて、現状のランキングを確認しよう。"王様、だーれだ"」
カズキが文言をとなえると、空中にランキング表が現れた。
画面をスクロールしていき、メンバーの順位を確認する。
<青山カズキ>
「相変わらずマウンティング力は上がっていても、肝心のランキングはほとんど動いてないな…今のところ僕達の中で一番順位が高いのは曜くんだけど、貴族になれそうでなれないところから変わってない」
ガレキ山での人助けのおかげで曜の順位はかなり上がっていたが、それでも貴族には程遠い。
<千羽つる子>
「もっとマウンティング力を上げないといけないという事でしょうか?」
<青山カズキ>
「そんな簡単な話ならいいけど…ん?」
と、ランキング表をスクロールしていたカズキが不意に目を細めた。
<五反田豊>
「どうかしましたか?」
<青山カズキ>
「このランキング上位の名前…僕達がミナトに来た頃から全然変わってないんだ」
カズキに促されランキング表に目をやると、そこには一位から七位までの最上位帯の人々の名前が掲示されていた。
『1―SUI YAKUMO―KING』
『2―TAKETORA YANAI― NOBLE』
『3―ROBINSON SON―NOBLE』
『4―RAKKAN TAKIZAKI―NOBLE』
『5―AFURI SAJI―NOBLE』
『6―WAICHI TAKAHARA―NOBLE』
『7―KINKATSU SHIGETA―NOBLE』
<彩葉ツキ>
「よっぽどすごい人達なのかなあ。普通にがんばっても追い抜けないくらいの」
<青山カズキ>
「でもさ、これを見てみなよ。スクショしておいた少し前のランキング表だ」
『1―SUI YAKUMO―KING』
『2―ROBINSON SON―NOBLE』
『3―TAKETORA YANAI― NOBLE』
『4―KINKATSU SHIGETA―NOBLE』
『5―RAKKAN TAKIZAKI―NOBLE』
『6―KAOTAN MORI―NOBLE』
『7―AFURI SAJI―NOBLE』
<青山カズキ>
「これがラブリーオーシャンでみんなと合流したとき」
『1―SUI YAKUMO―KING』
『2―ROBINSON SON―NOBLE』
『3―TAKETORA YANAI―NOBLE』
『4―KINKATSU SHIGETA―NOBLE』
『5―RAKKAN TAKIZAKI―NOBLE』
『6―KAOTAN MORI―NOBLE』
『7―AFURI SAJI―NOBLE』
<青山カズキ>
「これが三田くんの隠れ家で見たときのだ」
『1―SUI YAKUMO―KING』
『2―TAKETORA YANAI―NOBLE』
『3―ROBINSON SON―NOBLE』
『4―RAKKAN TAKIZAKI―NOBLE』
『5―AFURI SAJI―NOBLE』
『6―WAICHI TAKAHARA―NOBLE』
『7―KINKATSU SHIGETA―NOBLE』
<小日向小石>
「結構入れ替わってるように見えるけど…」
<青山カズキ>
「よく見るんだ。順位は多少動いてるけど、上位にいる貴族の名前は変わっていない」
<五反田豊>
「こうも全体のランキング変動が激しい中、上位を維持するのは相当難しそうですが…」
ミナトランキングダムの性質上、下剋上を起こしやすいゲームのはずだ。
本来であれば、貴族の顔ぶれは頻繁に入れ替わってなければおかしい。
にもかかわらず、曜達がこのミナトシティを訪れてからというもの、平民は誰一人として貴族のランクに食い込めていない。
曜だって、先程あれほどの量のポイントを稼いだにも関わらず、貴族には届かなかった。
これはどう考えてもおかしい。
<青山カズキ>
「絶対に動かない上位の貴族か…これはもしかして、尻尾を掴んだかもしれないな」
カズキが頷きながらそう呟いた――次の瞬間だった。
<システム音声>
「大幅なマウンティング力低下を確認。ランクが貧民になります」
全員のスマホから、都落ちを告げるシステム音声が鳴り響いた。
<彩葉ツキ>
「ええっ!? 急にどういう事!?」
ツキが驚きの声をあげる。
ここにいるメンバーは全員、安全圏の順位をキープしていたはずだ。
一斉に都落ちするなんて、ありえないはずなのに――
<システム音声>
「都落ちを避けるには…急いで…屋外に出てください」
システム音声は続けて、おかしな指示を発した。
<千羽つる子>
「屋外に出ろ…!? どういう事でしょうか?」
<青山カズキ>
「ひとまずここは従おう! みんな外に!」
指示に疑問を抱いている暇はない。
一刻も早く貧民の位から脱しなければ、レーザービームで全員殺されてしまう――曜達はドアから隠れ家を飛び出して外に出た。
<三田三太郎>
「なんだったんだよ今の…」
三田が空を眺めながら呟いた。
レーザービームが降り注いでくる様子はない――ランクは平民に戻ったようだ。
<システム音声>
「失礼。強引にシステムを変更したため少しエラーが生じたようだ。驚かせたのなら謝罪する」
と、おかしな事はさらに続いた。
カズキのスマホから突然強い光が照射され――建物の壁にデカデカと、丸い顔の絵文字が浮かび上がった。
<黒中曜>
「…は? な、なんだ?」
曜達は呆然と壁に浮かび上がった絵文字の顔を見上げた。
おかしな事が続き過ぎて、まるで理解が追いつかない――
<青山カズキ>
「…説明してくれるかい? システム音声の君。まあ…このタイミングで介入してきたって事は、正体は大体想像つくけどね」
カズキは大して動揺した様子もなく、絵文字の顔に向かって話しかけた。
<システム音声>
「大枠君の想像通りだ、青山カズキ」
システム音声はカズキの問いにそう答えた。
声音は無機質な機械音声だが、その話し方には人間味がある。
<青山カズキ>
「それは…君が判定をしてる人間だと認めたって事かな?」
<システム音声>
「正確には一部の判定だ。些末な判定はAIに任せている。それと個人ではない。
我々は限られた上位貴族で組織された――インフルエンサーとでも名乗っておこう」
曜達がシステム音声だと思っていたものは、人間の集団の声だった――カズキの読み通り、マウンティング力を計測していたのはAIではなかったようだ。
<青山カズキ>
「…そのインフルエンサーが僕達になんの用だい?」
<インフルエンサー>
「我々は交渉を望んでいる。それを受けるかは君達次第だ」
<青山カズキ>
「ふうん…詳しく話を聞く前にいくつか質問いいかな?」
<インフルエンサー>
「答えられる範囲で答えよう」
<青山カズキ>
「まず、君達はどうしてそんな権利を与えられているんだ?
人間が判定するという事になると、公平性が失われるように思えるんだけど」
<インフルエンサー>
「組織としての我々は以前より存在したが、判定を行うようになったのは、ごく最近の事だ。先の王様の時代までは、すべてAIによるマウンティング力判定が行われていた」
<青山カズキ>
「なぜ、そんな急に変更されたんだ?」
<インフルエンサー>
「八雲彗の意思と聞いている。意味はわからないが"ごほうび"だとも」
<五反田豊>
「"ごほうび"…ナンバーズ就任時に変えたという事ですね…」
ゼロによってナンバーズに抜擢された者には、就任時に"ごほうび"が与えられる。
それはウルトラごほうびとは異なり、願いを叶えられる範囲は限られ、ゼロの機嫌にも左右される。
彗はナンバーズ9に就任する際、この権利を使ってミナトランキングダムのルールを変えたのだろう。自らに、有利な形に――
<インフルエンサー>
「彼はAIによる厳密な判定よりも、人間による不安定な判定を望んだようだな。我々には極端な変動をするよう指示が出された。貧民降格による都落ちが多発しても構わないと」
インフルエンサー達は会話に応じて顔の絵文字をコロコロと切り替えていく。
笑っている絵文字、汗をかいている絵文字、サングラスをかけている絵文字――
<三田三太郎>
「アイツそんな事を…クソ…街が荒れたのはそのせいもあんのか…」
三田は口にくわえた葉っぱを強く噛みしめた。
彗に王座を奪われた元王様として、責任を感じているのかもしれない。
<青山カズキ>
「で、君達にはどんなメリットがあるの?」
<インフルエンサー>
「貴族の地位、並びに命の恒久的保証。それと貴族昇格の決定権だ」
<青山カズキ>
「なるほどね…」
貴族の顔ぶれが変わらなかったのは、システムによって彼らの地位が保証されていたかららしい。
いくらポイントを稼いだところで、平民が貴族に成り上がる事はできない――ミナトランキングダムは、最初から下剋上が不可能な仕様になっていたという事か。
<インフルエンサー>
「質問は以上か? なら、そろそろ話を戻そう。これからオダイバーの広場に来てもらいたい。続きはそこで話す。では」
映し出されていた顔の絵文字が消え、インフルエンサーの声が唐突に途絶えた。
<千羽つる子>
「正直、怪しく思えますが…」
<五反田豊>
「彼は交渉と言っていました。おそらく何らかの取引を持ちかけてくるかと」
曜達は顔を見合わせ、インフルエンサーが残していった言葉について議論する。
要求通りオダイバー広場に行くべきか? 罠の可能性はないのだろうか?
しかし、いくら議論を重ねても答えはなかなか出ず――
<彩葉ツキ>
「うーん…曜はどう思う?」
ツキは曜に判断を委ねた。
<黒中曜>
「確かに怪しいけど…貴族になるための近道になりそうなのは間違いない。向こうの目的は見えないけど…行こう」
インフルエンサーは怪しいが、他に道があるわけでもない。
手詰まりな現状を打破するためには、誘いに乗るしかない。
<彩葉ツキ>
「そっか…うん! これも彗を助けるためだしね!」
覚悟を決めた曜達は留守番役の三田と四つ子を隠れ家に残し、オダイバー広場に向かった。