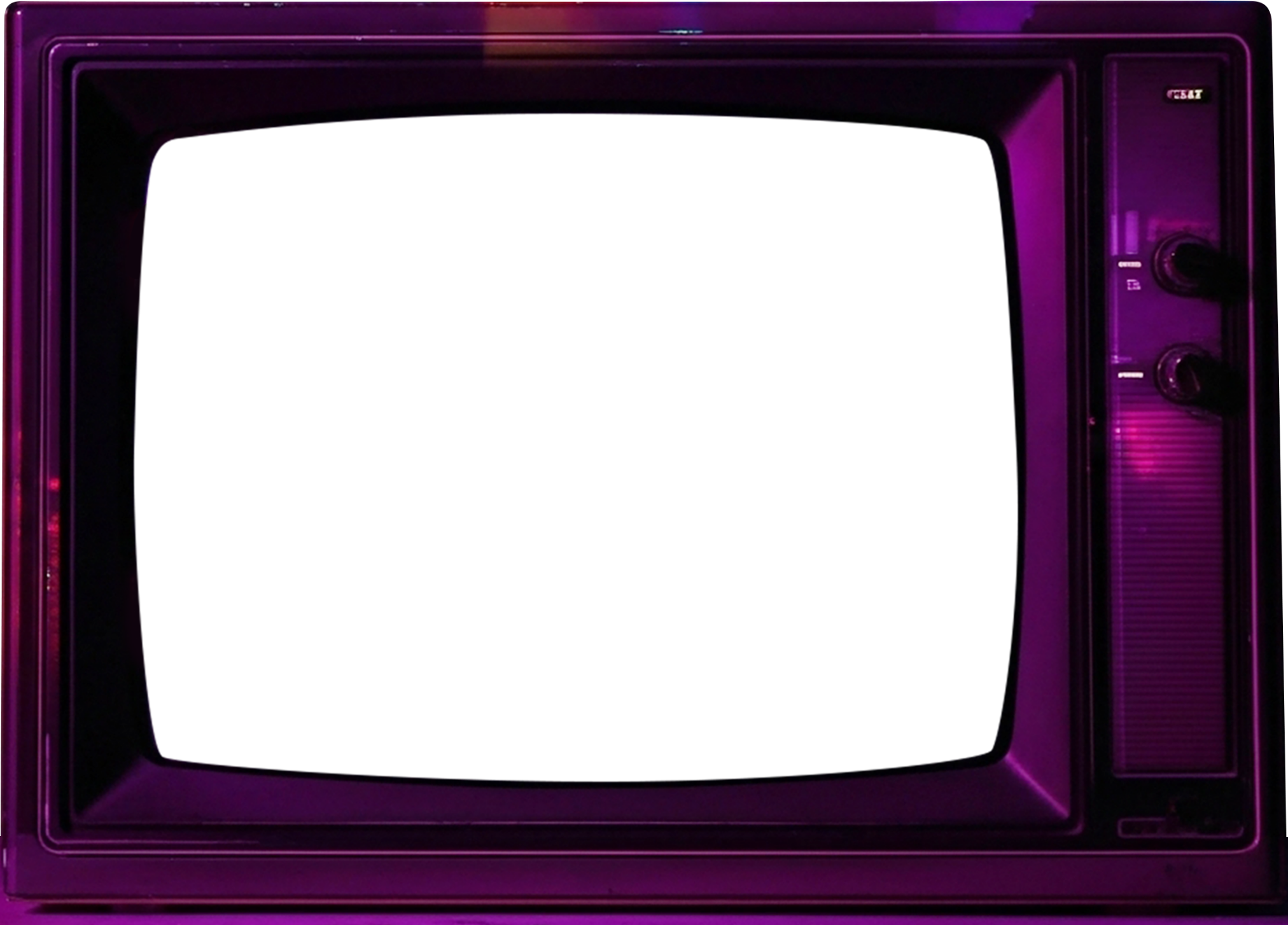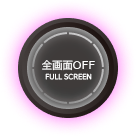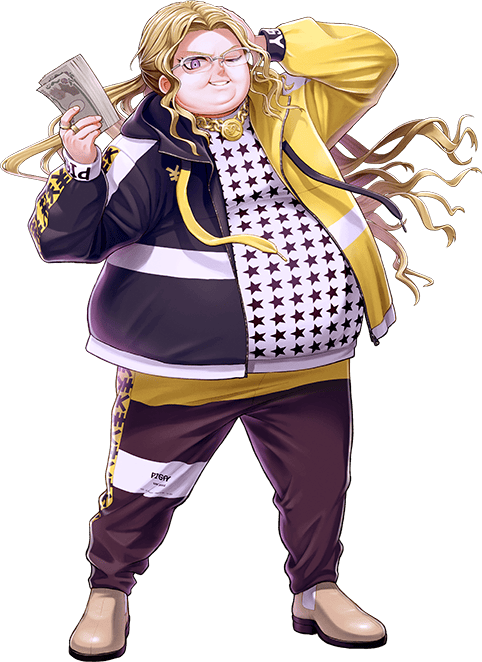12話「インフルエンサーからの試練」
オダイバー広場――つる子によると、ミナトシティの象徴とも言うべきオフィス街らしい。
周囲には近代的な高層ビルが建ち並び、ビルの向こう側には七色に光り輝く巨大な橋の姿が見える。
そんな広場の中央には、見上げるほど大きな人型ロボットのオブジェクトが置かれていた。
<彩葉ツキ>
「そういえばさ、このロボットってなんなんだろ?」
ツキはロボを見上げて首を傾げた。
<小日向小石>
「彩葉さん、知らないの!? "勇者騎士ブレイブダイバー"だよ!」
ツキの疑問に答える小石の目は、キラキラと輝いていた。
<五反田豊>
「私も昔、少し見た記憶があります。ずいぶん古いアニメじゃないですか?」
<小日向小石>
「続編もいっぱいあるしゲームもいっぱいあるから、結構見てるんです! 特にゲームで名作なのが――」
<インフルエンサー>
「到着したようだな」
と、小石の解説を遮るように、インフルエンサーの声が聞こえた。
カズキのスマホから強い光が照射され、ビルの壁にデカデカと絵文字の顔が浮かび上がる。
<青山カズキ>
「そっちはやっぱり姿を現さないか」
<インフルエンサー>
「リスク上、当然の判断だ。それより本題に移らせてもらおう。君達は八雲彗を倒そうとしている。相違ないな?」
<彩葉ツキ>
「倒すっていうか…とりあえずナンバーズなんてやめてほしいって思ってるよ」
沈んだ口調でツキが答える。
<インフルエンサー>
「事情は詮索しない。大事なのは我々も八雲彗に玉座から降りてほしいと望んでいるという事だ。黒中曜が王様になるというのならば、我々は協力する意思がある」
<青山カズキ>
「そんなの、君達が判定を操作すれば楽勝なんじゃないの?」
<インフルエンサー>
「王様のマウンティング力は我々には操作できない不可侵領域だ」
インフルエンサーの力をもってしても、王様には手出しできない――
やはりこのゲームにおいて、王様の地位は絶対的に保障されているようだ。
<黒中曜>
「けど、お前達は彗の下についていれば、貴族の立場が保証されているんだろ?
どうして王様の交代を望むんだ」
<インフルエンサー>
「八雲彗はあまりにも強過ぎるからだ。このままでは、奴は未来永劫ミナトシティの王として君臨し続けるだろう」
<青山カズキ>
「彗くんがいつまでも王様でいてくれた方が君達にとってはありがたいんじゃないの、って話をしてるんだけど?」
<インフルエンサー>
「長期政権の王などくだらん。移り変わりこそが、このゲームの面白さだというのに」
<千羽つる子>
「移り変わり…?」
<インフルエンサー>
「ミナトランキングダムのルールは非常に曖昧かつ流動的だ。その時々の王の価値観によって、"マウンティング"の解釈は変わり、ゲーム性もまたチェンジする。
我々は時々の王によって変更されたルールをいち早く察知し、それをミナトシティ全域に速やかにインフルエンスする事を使命としている。
八雲彗の治世の元では、我々は存在意義を失ったも同然だ」
<五反田豊>
「小難しい理屈を述べていますが…要するに運営気取りで統治ルールを楽しみたいだけでは?」
<インフルエンサー>
「捉え方は任せよう。我々としては、ゲームの流動性を保てるのなら他はどうだっていい」
<彩葉ツキ>
「んー、よくわかんないけど、彗に挑めるよう、曜を貴族にしてくれるって事だよね?」
<インフルエンサー>
「端的に言えばそうなる。だがこれは、我々にとってもリスクが高い計画だ。
君達が協力するに相応しいかどうか、証明してもらおう」
インフルエンサーは突然、不穏なことを言い出した。
曜達は警戒心を強めていく。
<千羽つる子>
「どうしろと言うのですか…?」
<インフルエンサー>
「八雲彗に挑めるだけの力があるか見極めたい。そのための相手を用意した。
それを倒せたら、協力を約束しよう」
<青山カズキ>
「値踏みされているようで気分はよくないけど、こうなったらこっちも利用させてもらおうか」
<五反田豊>
「これは一種のビジネスです。ときには割り切りも必要かと」
<黒中曜>
「わかった…やろう。で、俺達はどこの誰を倒せばいいんだ?」
曜達は臨戦態勢を取りながら左右前後を見回して、インフルエンサーが用意したという刺客の姿を探す。
<インフルエンサー>
「どこを見ている。お前達の相手なら、目の前にいるだろう」
言われて、曜は視線を正面に向けた。
しかし、目の前には誰も――その時だった。
突然、目の前に鎮座していたロボットの目が光り出した。
「ウォォオオオオオオオン…!」
<小日向小石>
「えっ!? ブレイブダイバーが…!?」
大型車のエンジンのような音を響かせて――ブレイブダイバーが動き出す。
ブレイブダイバーは左腕の鞘に格納していた大剣を引き抜いた。
剣を両手で握り、その切っ先を曜達に向ける。
<インフルエンサー>
「交渉の続きは、あれを倒してからだ」
<青山カズキ>
「やれやれ…これは文字通りの大物だね」
カズキが深々と溜息をつくのと同時に、ブレイブダイバーは曜達に襲い掛かってきた。
ブレイブダイバーの動きは、その図体の大きさからは想像もつかないほど俊敏だった。
アイススケートのように滑らかに地面を移動し、その勢いで大剣を振り回す。
<彩葉ツキ>
「は、はやぁ! あんなにデカいのになんで!?」
<黒中曜>
「みんな、距離を取れ…!」
動きが速い上に、攻撃の射程距離が広すぎる――曜達は為す術もなく、散り散りになって広場を逃げ続けた。
しかし、やられているだけの曜達ではない、最初に反撃の口火を切ったのはカズキだった。
<青山カズキ>
「あのロボットは構造上、自分の足元に向かって剣を振る事はできないみたいだ!
ビビらずに股下に入ってしまえば、かえって安全かもしれないよ!」
カズキは手本を示すかのように、突進してくるロボットの股下にするりと潜り込み――大木のような足にXBバットを改造した双剣で強烈な一撃を叩き込んだ。
バランスを崩し、ロボットは動きを止めた。
<五反田豊>
「今です! 皆で一斉に踵の部分を狙ってください! スラスターを故障させてしまえば、これまでのような高速移動はできなくなります!」
戦いながらロボの構造を解析していたのだろう、五反田が狙うべき箇所を皆に伝えてくれた。
曜達は勇気をもって一斉にロボの足に殺到し、各々の最大出力の攻撃を加えていく。
<彩葉ツキ>
「やった…! かなり動きが鈍くなってきたよ!」
滑らかな高速移動さえ封じてしまえばこちらのものだ。
曜達はヒット&アウェイの戦法で、ブレイブダイバーを少しずつ破壊していく。
動きの隙をついてブレイブダイバーの足に攻撃を加え――
そしてブレイブダイバーが剣を振りかぶったら一斉に距離を取り、攻撃を空振りさせる。
攻撃し、離れ、攻撃し、離れ――そんな嫌がらせのような攻撃を繰り返していく内に、ブレイブダイバーの足はボロボロになっていき――
ついにブレイブダイバーは両膝を地面について、完全に動きを止めた。
後はトドメを刺すだけだ。
曜は最後の一撃を叩き込むため、全速力でブレイブダイバーに向かって走り――
<青山カズキ>
「止まれ、曜くん。何かおかしい…!」
いち早く異変を察知したのはカズキだった。
追い詰められたブレイブダイバーは、これまでにはない動きを見せた。
ブレイブダイバーは剣を持っていない方の腕を曜に向け――手からロケットを発射した。
<黒中曜>
「くっ…!」
距離を詰めていたのがあだとなった。
曜は必死に横っ飛びするが、ロケットをかわしきる事は――
<小日向小石>
「危ない、黒中さん…!」
小石の鞄から飛び出してきた謎の黒い影が、曜の腕をギュッと掴んで引き寄せてくれた。
おかげで曜は間一髪のところでロケットをかわす事ができた。
<黒中曜>
「ありがとう小石…!」
<彩葉ツキ>
「決めちゃえ、曜ー!」
ツキの声援に背を押され、曜は再びロボットに向かって走り――
<黒中曜>
「終わりだ…!」
曜が顔面にバットを力強く叩き込むと、ロボットは仰向けに倒れ――両目から光がふっと消えた。
一同は疲れ切ったように息を切らしながらも、ホッとした顔を浮かべていた。
<黒中曜>
「はあ、はあ…な、なんとか倒せたな…」
<千羽つる子>
「まさか、オダイバーでロボット退治をするはめになるとは…まさに奇想天外ですわ」
<小日向小石>
「倒せて嬉しいけど、僕は少し複雑な気分だよ…自分の手で、大好きなブレイブダイバーを壊す事になるなんて…」
精魂尽き果てるまで戦い、満身創痍になった曜達。
しかし、その甲斐あって――
<システム音声>
「大幅なマウンティング力上昇を確認。おめでとうございます。ランクが貴族になりました」
曜の頭上の数値が急激に上昇し、貴族昇格のアナウンスが聞こえてきた。
インフルエンサーは約束を守ってくれたようだ。
<インフルエンサー>
「君達の力は見せてもらった。昇格おめでとう、黒中曜」
<青山カズキ>
「おかげで貴族入りできたよ。…君達の思惑通りにね」
<インフルエンサー>
「八雲彗に挑む権利は与えた。ここから先は君達の努力次第だ。我々は以降、関与しない」
<千羽つる子>
「あとは高みの見物ですか…いい御身分ですね」
皮肉を口にするつる子。自らは安全圏にいるくせに、曜達にだけ危険を強いるインフルエンサーに、思うところがあるのだろう。
<インフルエンサー>
「最後にひとつだけ忠告しておく。我々の事は誰にも言ってはならない。当然、八雲彗にもだ」
<青山カズキ>
「へえ…もしそれを破ったらどうなるの?」
<インフルエンサー>
「貴族の権利剥奪だけでは、済まないとだけ言っておこう」
映し出されていた絵文字の顔が消え、インフルエンサーの声は聞こえなくなった。
<五反田豊>
「最後に脅しですか…つくづくビジネスの相手としては最悪な方でしたね」
<小日向小石>
「でも…やっと準備ができたんだ。今は喜んでおこうよ!」
小石の言う通りだ。
形はどうあれ、曜が貴族に昇格できた――これで彗に挑む事ができるのだから。
と、スマホが「ピロン」と音を鳴らした。
<NINE(三田三太郎)>
「よう、どんな塩梅だ?」
グループチャットに書き込まれていたのは三田からのメッセージだった。
<NINE(青山カズキ)>
「順調だよ、ようやく貴族になれた。今後の作戦もあるから一旦戻ろうと思う」
<NINE(三田三太郎)>
「そりゃ朗報だな! あ、でも俺達も今、外出てんだよ!」
<NINE(青山カズキ)>
「こんな時に随分と悠長だね」
<NINE(三田三太郎)>
「うるせーな…でも、ちょうどいいや。お前達もこっち来いよ一度落ち合おうぜ」
<NINE(千羽つる子)>
「今どちらにいるんですか?」
<NINE(三田三太郎)>
「アザブ交差点の辺りだ。見せておきたいものがあるんだよ。特にカズキと五反田にな」
<NINE(五反田豊)>
「見せたいものとは?」
<NINE(三田三太郎)>
「見てのお楽しみだ。ま、いいから来いって」
思わせぶりな三田のメッセージに呼び出され、曜達はアザブ交差点に向かう事にした。